

物語に出会う
見えているものが、すべてではありません。
あなたが歩いた、あの穏やかな丘。
あなたが触れた、あの冷たい石。
そのひとつひとつには、
目には見えない、壮大な時間が眠っています。
野焼きが生み出す風景
草原に火を灯す理由

春、平尾台は燃える。
人々が、自らの手で、この美しい草原に火を灯す。一見、自然を破壊しているかのような、この“野焼き”。時には、痛ましい事故さえ引き起こしてきた。なぜ、彼らは、それでも火を灯し続けるのか。
それは、この風景が、ただの「自然」ではないことの証だ。
1000年の生活の知恵、絶望と再生の歴史、そして「守る」ことと「使う」ことの葛藤。
この炎には、平尾台を生きてきた人々の、全ての物語が燃えている。
1章:人と自然が、共作した風景

その大胆さは周到に練られた計画と、長年の経験に裏打ちされている。
毎年2月から3月にかけて、平尾台では「野焼き」が行われる。地域の人々の手によって高原の草をすべて焼き払う、ダイナミックな営みである。
野焼きの直後、この丘を訪れた者は、いつも見られる青々とした草原を目にすることはない。そこにあるのは、黒く焼けた大地と、そこから突き出すようにして白く輝く、無数の石灰岩。まるで別の惑星に来たかのようなその非日常的な風景は、見る者を圧倒する。
そして夏が近づくにつれ、黒い大地からは緑の若い芽が一斉に顔を出し、再び、生命力あふれる草原へと姿を変えていくのだ。
木々がほとんどなく、どこまでも草原が広がるこの風景。「自然のまま」と思われがちだが、実は、そうではない。この野焼きという「破壊と再生」のサイクルを、人々が何百年も繰り返してきたことによって守られている、人と自然が共作した、特別な風景なのである。
その起源は、かつての生活の知恵にある。この高原の茅(かや)が、家畜の餌や茅葺屋根の材料として使われていた。刈り取った後に残る枯れ草を処理するために火が使われたのが、その始まりだ。
2章:継がれる火、受け継がれる想い

野焼きは、緻密な計画のもとに行われるチーム作業だ。10月の、まだ野焼きには早い時期に行われる「防火帯焼き」もその一つ。火が燃え広がらないよう、あらかじめ火の通り道にある草を焼き、緩衝地をつくるのである。
なぜ、これほど手間のかかる営みが、今日まで続いているのか。その背景には、風景に刻まれた、壮絶な歴史があると、野焼き頭の前田康典さんは語る。
昭和52年、広谷湿原で、痛ましい事故が起こった。野焼き作業中の数名の消防士が、火に巻き込まれて命を落としたのだ。野焼きの恐ろしさを、誰もが骨身に染みて認識させられた出来事だった。この事故を受け、責任の所在や安全管理が厳しく問われ、平尾台の野焼きは、ここから18年間ものあいだ、中断されることになった。
かつて、野焼きの主な目的は、害虫駆除といった、より生活に密着したものであった。しかし、中断された長い年月は、人々に、その価値を問い直させた。失われゆく草原の風景を前に、野焼きの意味は「草原景観の維持」という、より大きなものへと変わっていったのだ。

火を扱う以上、リスクはゼロにはならない。特に火は風を受けて山を駆け上がる。条件が揃えば、時速30キロに達するという。それは、人間が走って逃げられる速さではない。
野焼きは「行うべきではない」ものではなく、「行わなければならない」もの。そう信じる人々が立ち上がり、設立されたのが「平尾台野焼き委員会」だ。麓の東谷地区の各種団体が連携し、火を安全に扱い、景観を守るための、新しい体制を築き上げた。
前田さんは、この委員会で「野焼き頭」として、15年間、現場を率いてきた。火の扱いは、天候、風、地形を読む、長年の経験と土地勘が全てだ。マニュアル化できない、地元に根ざした知識と覚悟。それを受け継ぐ人々の存在こそが、今の平尾台を支えている。
3章:開発と共生のはざまで
平尾台の歴史には、もうひとつ見すごせない側面がある。明治時代末期から、ここは旧日本陸軍の演習地だった。戦争が終わり、軍が撤退すると、平尾台は再び人々の場所となる。戦後の物資が乏しい時代、残された兵舎などを頼りに、多くの開拓者がこの地に移り住み、岩だらけの土地をその手で耕した。
現在、平尾台は大きく三つの顔を持つ。国定公園として保護される「自然区域」。石灰岩を採掘する「産業区域」。そして、人々が暮らす「生活区域」。
採掘所で今も行われる石灰岩の採掘は、日本の産業と、私たちの快適な生活に、必要不可欠な資源を供給している。一方で、地域の人々はこの場所の、かけがえのない風景を守るべきだと考えた。「自然のままに残すべき場所がある」という声が、国定公園の指定へと繋がったのだ。
平尾台の歴史とは、資源と景観、生活と自然、開発と保全という、異なる価値観が、常に対話し、葛藤し、そして共存してきた歴史そのものである。
私たちは、この問いに、どう向き合えばいいのか。資源が私たちの生活を豊かにしてきたことも、風景が人の心を潤してきたことも、どちらも、変えることのできない事実なのだから。
4章:未来へ灯す、炎
だからこそ、問い続けなければならない。この風景を、どう未来へ受け継いでいくのか。
前田さんは言う。「平尾台は、山の上だけのものではない」と。
それは、この大地が、私たちの暮らしを支える「資源」であり、心を潤す「風景」であり、そして、自然とどう向き合うべきかという「答え」と「問い」の両方を与えてくれる、かけがえのない場所だからだ。
野焼きの炎が受け継いできたのは、ただの技術ではない。
この場所を愛し、守り、悩み、そして未来を信じてきた人々の「想い」。
その熱い想いこそが、平尾台を「みんなの財産」にしているのである。

風が、丘を渡っていく。あなたはこの風景の中に、どんな未来の物語を見つけますか。
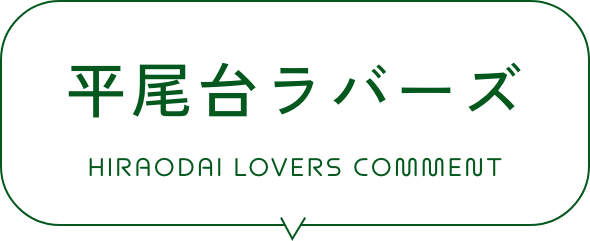
人気の記事POPULAR





















地殻変動の跡を、この足で確かめに行きましょう。